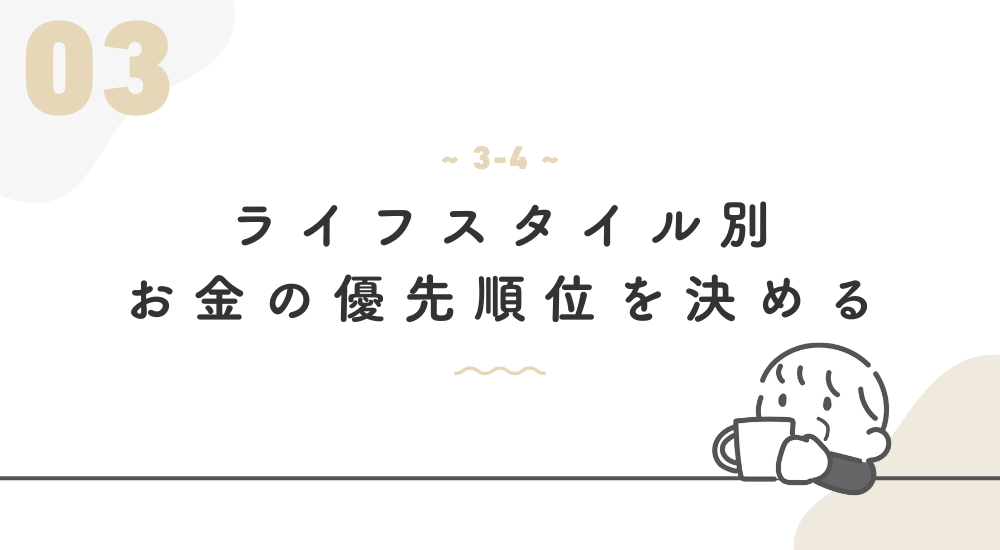節約やお金の管理というと、多くの人が「とにかく支出を減らそう」と考えます。
でも、それでは長続きしません。
なぜなら「我慢」による節約は、どこかで反動が来るからです。
僕もかつては「使わないこと=正しい」と思っていました。
食費を切り詰め、趣味も我慢し、出費をどんどん削っていく。
たしかに一時的にはお金は貯まりますが、気持ちはどんどんすり減っていきました。
結局ストレスに耐えられず、ある日どかんと浪費してしまう…。
そこで気づいたのは「お金には優先順位をつけること」が大切だということです。
自分にとって大事なものに使い、優先度の低いものを削る。
そうすれば我慢ではなく「選択」に変わり、無理のないお金の管理ができるようになります。
お金の使い方=ライフスタイルの写し鏡
人によって大事にしていることはまったく違います。
- 食べることが大好きで、外食や食材にお金をかけたい人
- 趣味や学びにワクワクを感じる人
- 家やインテリアにこだわって、暮らしの空間を整えたい人
僕の場合は「学び」と「暮らしの快適さ」に優先順位を置いています。
教材やセミナーへの投資は迷わないし、家の中を快適にするアイテムにはお金を回す。
逆に、洋服や車などにはあまりこだわらないので、そこは削る。
このように「何に使うと満足度が高いか」を知ることは、単なる家計管理以上の意味があります。
それは「自分らしいライフスタイル」を形にすることでもあるんです。
優先順位を決める3つのステップ
では、どうやって自分のお金の優先順位を決めていけばいいのか?
ここではシンプルな3ステップを紹介します。
- 支出が多いのに満足度が低いもの → 見直す余地あり
- 支出は少ないのに満足度が高いもの → 増やしてもいい投資対象
こうして整理すると、意外な発見があります。
僕もやってみて「コンビニのちょい買い」は支出が多いのに満足度が低いことに気づき、ほぼゼロにしました。
逆に「カフェ時間」は満足度が高い割に支出は小さいので、むしろ増やすようにしています。
実践ワーク:わたしの満足度チェックシート
ここでおすすめなのが「わたしの満足度チェックシート」を使った整理です。
- 縦軸:満足度(高い⇔低い)
- 横軸:支出額(多い⇔少ない)
この4つに自分の満足+支出を振り分けてみましょう。
- 満足高・支出低 → 積極的に残す
- 満足高・支出高 → 生活の柱・工夫して効率化を考える
- 満足低・支出低 → 無理に削る必要なし(ただし増やさない)
- 満足低・支出高 → 今すぐ削るべき浪費
このワークをやると、自分のお金の使い方が「可視化」されます。
頭の中で考えるよりも、シートに書き出すと驚くほどスッキリしますよ!
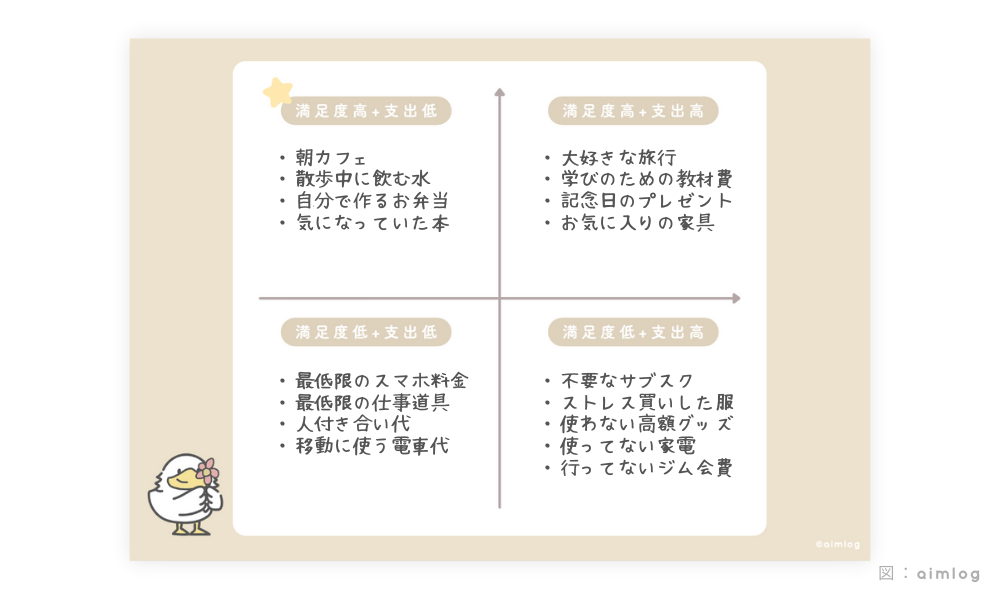
お金を使うことにモヤモヤする瞬間が、人生には訪れます。
- そもそも手持ちが少ない時
- 節約などである程度お金を貯めた時
もちろん、お金を使わず満足する方法もあります。
ただ、お金を使うことでも得られる充実度もあるんです。
「どれだけ自分を満たしているか」という視点を合わせること
そうすることで、暮らしの満足度を見える化できます。
そして今このシートを書いたあなたは、「お金の自分軸」ができた状態です。
「周りから言われた、SNSやテレビで見た」そうした他人軸のお金の使い方がなくなり、「お金を使う自信」が持てるはず。
つまり、書き出した時点で「自然と、自動的に」お金の使い方で迷わなくなるんです。
定期的にシートを更新し、振り返る習慣も設けると、さらに暮らしをアップデートできるので、1回で終わらないよう繰り返しやってみてください!
僕が得られた気づき
この整理をしたことで、僕は「お金の流れ=自分の価値観」だと理解できました。
お金をどう使うかは、自分が何を大切にしているかの表れです。
昔は「節約=正しい」と思っていた僕も、今は「使うところにはしっかり使う」方が豊かだと感じています。
だからこそ、自分にとっての優先順位を明確にすることが大事なんです。
まとめ
- 我慢の節約では続かない。大事なのは「優先順位」をつけること
- 支出をカテゴリ分けして「満足度」と「支出額」を見比べる
- 高満足×高支出は効率化、高満足×低支出は増やす
- 低満足×高支出は浪費。ここを削るだけで余白が生まれる
- お金の使い方は「自分の価値観の写し鏡」
お金の優先順位をつけることは、ただの節約テクニックではなく「自分らしい生き方」を選ぶことでもあります。
ここで整理した価値観は、この先「稼ぐ」「増やす」といったフェーズでも大きな指針になってくれるんです。
何度も何度もワークを行い、自分ごとに落とし込めるまでやってみてください。