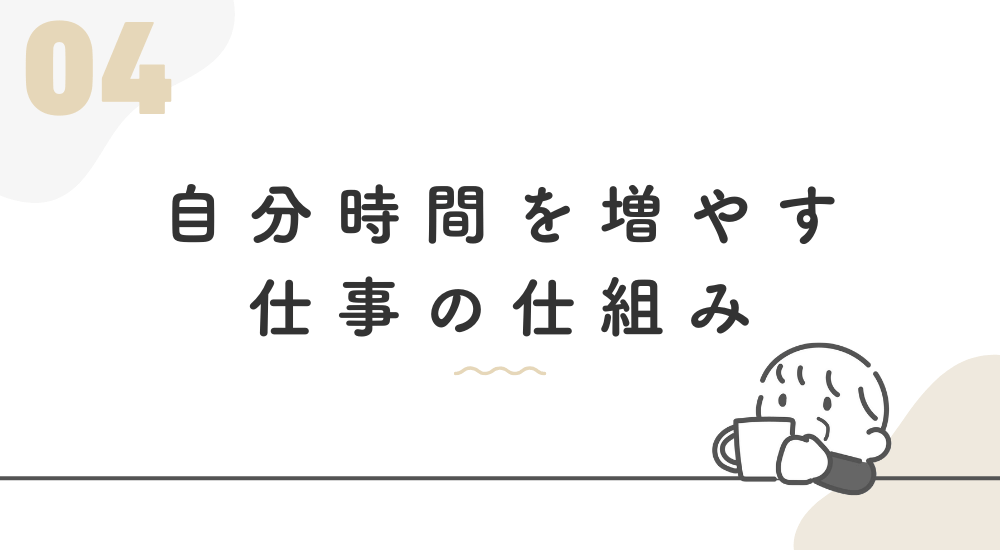この章では、「働き方」と「暮らし」の関係を見直し、仕事に振り回されないための仕組みを学んでいきます。
僕自身、かつては「仕事=生活のすべて」という感覚で働いていました。
とはいえ、長時間労働で疲れ果て、家に帰っても何もする気力がなく、ただ次の日に備えて眠るだけの日々。
給料は入っても、心の余裕はまったくありませんでした。
そんな僕が「働き方の自動化」に意識を向けてからは、少しずつ暮らしが変わっていきました。
仕事の一部を仕組み化したり、AIに任せられる部分を任せることで、自分の「時間」と「エネルギー」を取り戻せるようになったんです。
結果的に、その時間を使って暮らしを豊かにする行動をするように。
たとえば「読書や散歩、家族との時間、副業への挑戦」に回すことができました。
つまり、この章のゴールは「仕事のために暮らす」から「暮らしのために仕事を活用する」へと視点をシフトすることです。
4章で書いてあること
仕事のあり方が暮らし全体にどう影響するのかを整理します。
「自分だけが動き続ける働き方」と「仕組みを動かす働き方」の違いを知り、選び方を考えます。
最新のツールやAIをどう使えば、自分の負担を減らしつつ価値を生み出せるのかを解説します。
収入=お金だけではなく、「時間」という資産をどう確保していくかを考えます。
シートを使いながら、自分の働き方を整理し、AIと共に仕組み化の設計をしていきます。
なぜ「働き方の自動化」が必要なのか
働き方を自動化する目的は、単に楽をすることではありません。
むしろ逆で、僕たちは「本当に大切にしたいこと」にエネルギーを注ぐために、仕組み化が必要なのです。
例えば、あなたは次の問いにどう答えますか?
今まで僕自身、オンライン上で面談等を行い、たくさんの声を聞いてきました。
そしてこの問いに返ってきた言葉の大半は「暮らしを大切にしたい」と答える方ばかりでした。
この「暮らし」という言葉の中には、「家族と笑顔で過ごしたい」「愛犬・愛猫と穏やかに暮らしたい」という意味が込められています。
でも現実には、仕事に振り回されて暮らしが後回しになっているケースが多いのです。僕もその一人でした。
だからこそ、僕たちに必要なのは「暮らしを基準に働き方を設計する」という発想です。
時間を最優先に、心の余裕を作っていく。
そのための道具として、仕組み化やAIが役立ちます。
この章を読んだあとの姿
この章を読み終えたとき、あなたは次のような視点を持てるようになります。
- 仕事を「暮らしの一部」として捉え直し、無理のない働き方をイメージできる
- 自分がやらなくてもいい作業を見極め、任せる工夫ができる
- 時間という資産を守ることが、収入や豊かさの土台になると理解できる
- 実際に自分の働き方をシートに書き出し、ChatGPTを使いながら具体的な改善を始められる
つまり「理想的な暮らし」を描くだけでなく、そのために必要な働き方をデザインできるようになるのです。