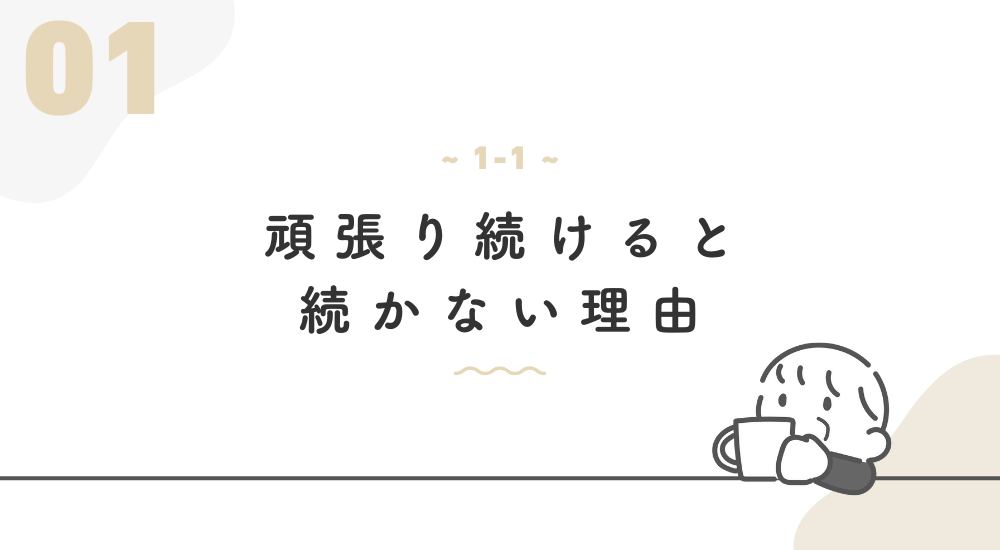「よし、明日から頑張ろう!」
僕も昔はそうやって気合いを入れては、数日で疲れてやめてしまうことを繰り返していました。
あなたも同じ経験がありませんか?
どれも「やる気」で始めて、「やる気」が切れたらやめてしまう。
この教科書で一番伝えたいことのひとつは、「がんばり続ける必要はない」ということです。
むしろ、がんばり続けようとするから続かないんです。
実は知らない「がんばる」の限界
人の意思の力は、心理学では「自制心(ウィルパワー)」と呼ばれています。
スタンフォード大学の研究によると、この自制心は筋肉のように使えば疲れてしまうものだそうです。
つまり、最初はやる気があっても、毎日「我慢」「努力」を繰り返していると、やがて消耗してしまう。
そして、どんなに真面目な人でも、ある日突然「もう無理」と思ってしまうんです。
これを心理学では「自制心の枯渇」と呼びます。
がんばり続けるやり方は、必ずどこかで息切れしてしまうんです。
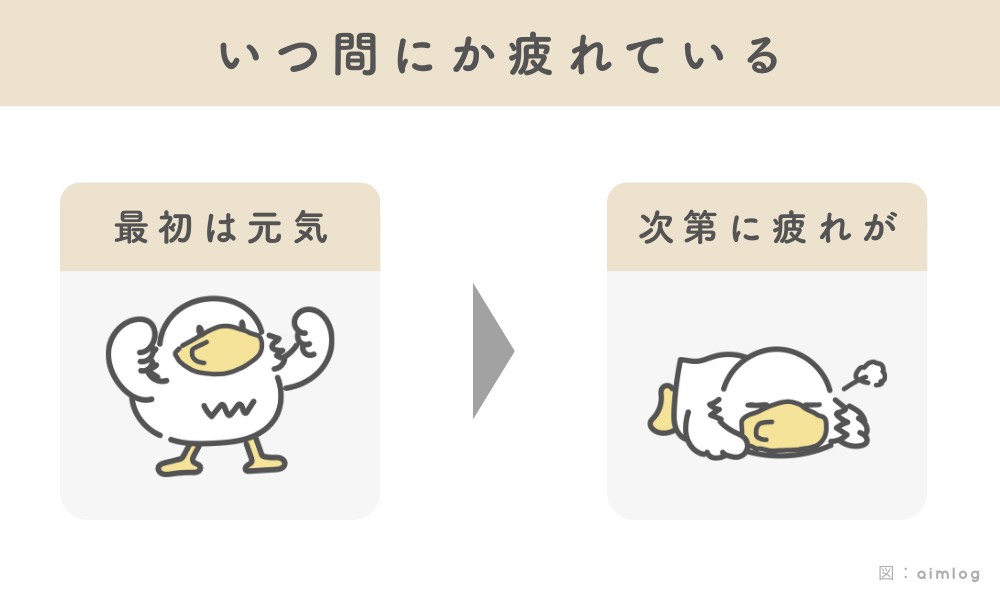
自然とできる仕組みを作る
だけども、「じゃあ何もしない」というわけにはいきませんよね?
ならどうすればいいのか。
僕がたどり着いた答えは「自然とできる仕組みをつくること」でした。
例えば、
これらは、いわゆる「環境デザイン」と呼ばれるものです。
人は「意志」よりも「環境」に強く影響を受ける。
心理学の行動経済学でも「選択の仕方が変われば行動も変わる」と言われています。
つまり、がんばる必要はない。
仕組みを作ってしまえば、自然に体が動くんです。
僕の体験談:がんばるをやめたら続いた
たとえば僕も昔は、毎朝「よし、早起きしよう!」と気合いを入れていました。
でも3日坊主どころか、1日で寝坊してしまうこともありました。
そんな僕が続けられるようになったのは、「がんばる」をやめて「仕組みに任せる」ようになってからです。
たとえば、
- スマホをベッドから離れた場所に置く
- カーテンを薄手にして日光が入るようにする
- 寝る前に机の上に日記を置いておく
これだけで、無理なく起きて、机に向かえるようになりました。
「自分ががんばっている」という感覚すらなく、ただ「自然にそうなっている」。
この感覚が手に入ったとき、初めて「続けられる人」になれたんです。
がんばらないための3つのポイント
ここで、がんばり続けなくても習慣が続くための基本を3つにまとめます。
→例:机の上からスマホを遠ざける、すぐ使えるように道具を出しておく。
→例:「歯磨きの後に日記を書く」「コーヒーを飲んだら勉強する」。
→例:筋トレは腕立て1回から、日記は1行から。
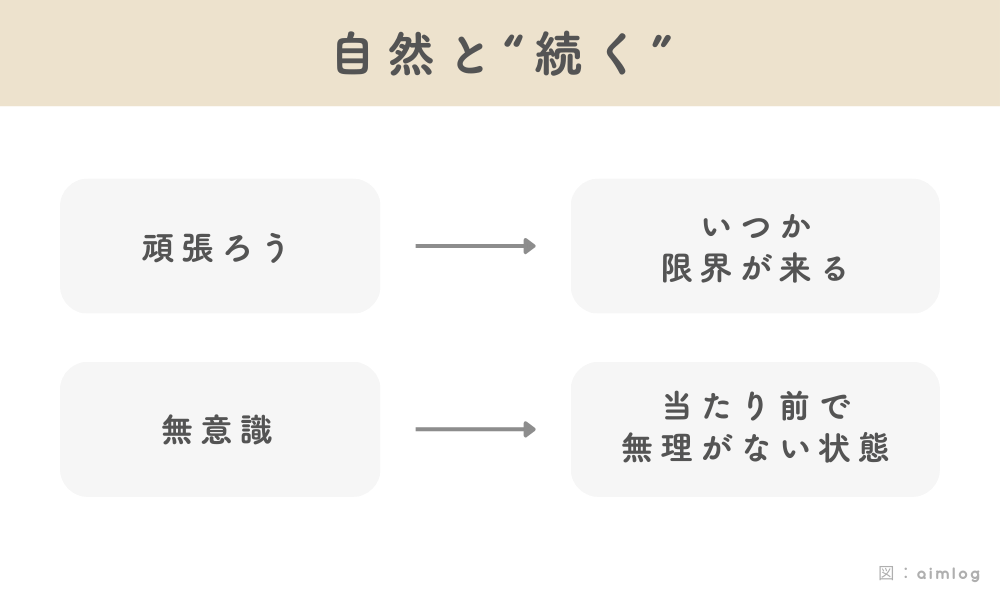
「がんばらない」は甘えじゃない
ここまで読むと、「でも、がんばらないなんて甘えじゃないの?」と思う人もいるかもしれません。
でも実は、成果を出している人ほど「がんばらない仕組み」を持っています。
ビジネスの世界では「仕組み化」が当たり前で、暮らしでも同じことが言えます。
あなたの会社でも社長一人が働いているわけではないですよね?
営業部がいて、経理部がいて、店頭に立つ人がいて…そうして会社は回っているんです。
これを「他の部署の人は頑張っていない」と判断するのは、違いますよね。
目の前にそうした仕組みを作って、回している環境があるのなら、あなただけやってはいけない理由になりません。
つまり、「がんばらない=ズル」ではなく、「がんばらない=賢い」んです。
ただ何もしないわけではありません。自分にとっての本質「理想の暮らし」を過ごすために、”やめる”のです。
まとめ:続く人は、がんばらない人
- がんばり続けると、自制心が消耗して必ず疲れる
- 環境や仕組みを作れば、自然に続けられる
- 小さな工夫で、「やる気ゼロでも続く暮らし」が可能になる
この教科書では、「がんばる」を卒業し、「自然とできる仕組み」を一緒に作っていきます。
最初の一歩は、「がんばろう」と思わないこと。
そこから、本当に続く習慣づくりが始まります。